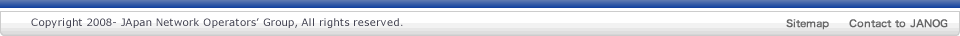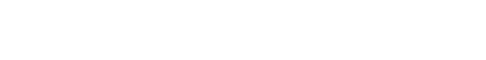


プログラム選考の裏側
こんにちわ。JANOG37 プログラム委員長のビッグローブ土屋太二です。
今回はニュースレター第3回目として、JANOG37のプログラム選考の裏側についてご紹介させていただきます。
JANOGミーティングは、常設の 運営委員会 と、ミーティングごとに公募される 実行委員会 によって作られています。
ミーティングごとにメンバーが異なるため、プログラム選考方法もミーティングの都度検討しています。
これまでのミーティングで発見された課題やプログラムの応募傾向、参加者からいただいたご意見などを踏まえた上で、その時々で最適なプログラムの選考方法を検討し、方針を決めています。
JANOG37のプログラム選考を例にご紹介します。
JANOGでは1ヶ月程度のプログラム応募期間を設けています。そしてその後、全ての応募について、プログラム委員全員で精査し、テーマの有用性について時間をかけて議論します。
JANOG37の場合では応募締切後の2週間程度をかけて、それぞれの応募について「プログラムを通して何を伝えることができるのか」「プログラムを聞いた参加者は、何を会社や組織に持ち帰ることができるのか」「JANOGならではの、参加者を巻き込んだ議論を展開できるか」など、様々な観点で意見を出し合い議論しました。
応募内容の文面だけでは「応募に至った背景」や「プログラムを通して伝えたいテーマ」が推測しづらいものについては、時間の許す限り応募者にご協力いただいて情報をもらうようにしました。


「プログラム検討の風景」
次に、プログラムの選考についてです。事前に十分な議論をしているものの、実質一回のミーティングですべての応募に対して採否を決めることになります。JANOGミーティングの出来を決める重要な位置づけであり、応募者の方にとってのチャンスを左右する難しい立場でもあるため、プログラム委員としては最も神経を使うところであると同時に、最もやりがいのあるところでもあります。
JANOG37ではプログラムを選考するにあたり、プログラム委員それぞれが考える「最高のJANOGタイムテーブル案」を提案しあうプレゼン大会を実施しました。
これは各プログラム委員がそれぞれの経験や知見を元に、自身が考え抜いた「採用したいプログラム」と「JANOG参加者に活発に議論してもらえるための発表時間帯やプログラムの並び」を取り入れたタイムテーブル案をプレゼンし合います。そして最後に、各々がベストだと思うタイムテーブル案をお互いに投票しあうことで、採用プログラムおよびタイムテーブルを決定する仕組みを取り入れました。
JANOG37のプログラム委員では、ISP、IXP、コンテンツ事業者、クラウド事業者、DC事業者、SIer、メーカ、研究者、若手、ベテランといった多種多様なメンバーに恵まれました。メンバーそれぞれが感じているプログラムへの期待やJANOG参加者への想いを「タイムテーブル案」という形で表現しあうことで、各メンバーの持つ価値観や創造力を共有することができ、非常に幅広い視点で議論をすることができました。この取り組みを実施した結果、初参加メンバーのタイムテーブル案が、大多数の賛同を得た上で採用されました。

「タイムテーブル案プレゼン大会」
このようにして作られたJANOG37 タイムテーブルがこちらになります。
たくさんの魅力が詰まったプログラムタイムテーブルを、当日思う存分楽しんでいただければと考えています。