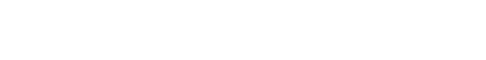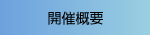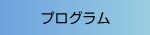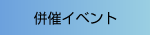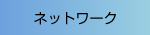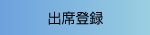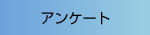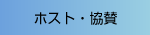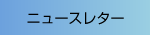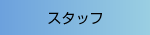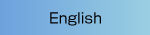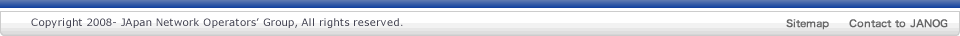インターネットガバナンスがよくわからない? 本音でひざをつき合わせて語るBoF~ “I CAN” not understand ICANN? ~
- 発表者
- 岡田 雅之 (一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター)前村 昌紀 (一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター)石田 慶樹 (日本インターネットエクスチェンジ株式会社)川上 雄也 (インターネットマルチフィード株式会社)田島 弘隆 (Genie Networks)協力: ISOC-JP/JPOPF
- 概要
理系出身の技術者は目の前のテクノロジーやプロトコルにわくわく、どきどき、しがちで、いわゆる「文系」な方々の考え方と接触は、なんかよくわからない、などと、得てして避けられている傾向があるといわれています。
しかしながら、今、技術者が「インターネットへ参加する」ことできる根拠は何なのでしょうか?
例えば、IPアドレスについてはアドレスポリシーやレジストリの技術文書であったりします。その他、通信回線や国際間の通信には、法律や憲法、はたまた国際条約などはほとんど技術者の関係が少ないところで議論され、作られてゆきます。
技術者が技術的自由を維持し続けるためにはこのような人々の動向に常に注目し、理系であったが敢然と立ち向かって道を作った先人たちの努力を無にするようなことになっては残念な結果となってしまうことでしょう。
国外においてはIETFやRIPEといった技術コミュニティでも、この分野において技術者としてどう関わっていくのかの検討が進められています。
例えばIETFではNSAによる情報監視活動への対策がインタネットガバナンスの文脈でも議論される中、技術標準面からセキュリティ強化のための検討を進めるとの方針が総意を得られ、プロトコルレベルで具体的な検討を進めています。
そして、IABでインターネットガバナンスに特化したMLがあり、最新の動向のうち、IETFに関わる議論がされています。
また、欧州における運用者のコミュニティであるRIPEではこれに特化して議論を行うワーキンググループが存在し、RIPEカンファレンス毎に議論を行っている状況です。
このように国外の技術コミュニティでは、自分たちの立場から議論に関わる検討を進める動きもある中、国内においては真にその必要性や重要性を体感してもらう状況には行き着いていないのが現状と言えるのではないでしょうか。
このBoFでは、幅広いトピックスを扱うインターネットガバナンスの分野において、技術コミュニティにも関わりがあると思われる議論をパネリストが簡単にご紹介します。そのうえで、日本の技術コミュニティとして今後重点を置いて関わるべきトピックスはなにか、どういう情報提供やコミュニケーションがあると、技術者としても関わりやすいのか、運用者の立場からみなさんの声を是非聞かせてください。
運用者の視点から国内での検討をどう進めるか、ひざを突き合わせて、ワイワイと一緒に議論していきましょう!
- 資料
ソーシャルボタン
個別チュートリアルページにもソーシャルボタンを用意しています。おすすめのチュートリアルや気になったチュートリアルに「いいね」をつけましょう。
(最終更新日: 2014.08.01)