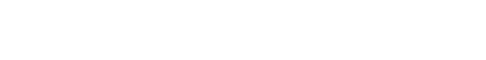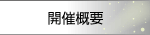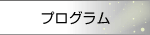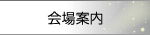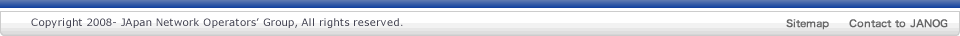JANOG29.5
プログラム詳細
- タイトル
-
[ライトニングトークplus]
今、IGPの話しませんか? - 概要
-
いよいよIPv4が枯渇し、IPv6のネットワークの為のデザイン検討が色々な所でされています。
ネットワークデザインはどう組むと良いのでしょうか?
IPv4/IPv6のデュアルスタックネットワークを構築する時、いくつかの考えがあると思います。
- 1.デュアルスタック・デュアルプロセス・シングルトポロジー
-
IPv4のネットワークデザインをそのまま、IPv6でも世襲する考えです。
OSPFv2を使用してるのであれば、IPv6ではOSPFv3を使用し、同一な論理トポロジーを構築します。
マルチプロセスを管理する必要があり、同じ性質のプロトコルであるものの細かな機能の差がありえます。
- 2.デュアルスタック・シングルプロセス・シングルトポロジー
-
コアネットワークにIPv4/MPLS(もしくはISIS)を導入し、シングルプロセスで管理する手法です。エッジには6rd/6PEなどを用いて、コアはIPv6に対するケアをしません。
また最小限度の機器のアップグレードで済むという特徴もあると思います。
機器のアップグレードは大規模にはなりますが、逆にコアでIPv6のみを動かし、RFC5838を使って、デュアルスタック化するという考えもあります。
- 3.デュアルスタック・デュアルプロセス・デュアルトポロジー
-
広大なホスト空間を持つIPv6に適したネットワークを考慮し、それぞれのアドレスファミリーで適したネットワークを構築する手法です。
レイヤー3スイッチで構築されたネットワークが多い昨今では、IPv4はルーティングさせてIPv6はスイッチされるという事が用意に出来るために、物理配線は変更せずにこの様な論理ネットワーク構成を組むことが可能です。OSPFの様にアドレスファミリー毎のマルチトポロジーに対応していなかったISISではRFC5120を使って、実現する事も出来ます。
- 発表者
-
土屋 師子生(シスコシステムズ合同会社)
- 資料