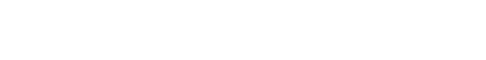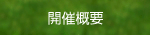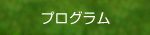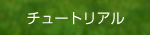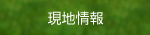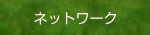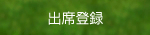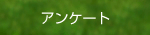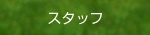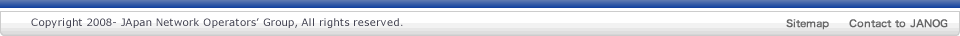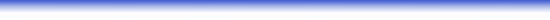
運用チームの作り方
- 概要
インターネットは眠りません。
そんなインターネットは複数人で交代勤務をしながら支える必要があるのですが、チームを作り、維持するのは意外と大変です。
知識や情報をどうやって共有するか、どんなツールを使うか、モラルはどうやって保つか、教育をどうするか、シフトはどう組むか、、、、
うまいやり方、をみんなで共有したいと思っています。
- 発表者
豊野 剛 (日本電信電話株式会社)
吉村 知夏 (NTT America, Inc.)
高峯 誠 (さくらインターネット株式会社)
- 公開資料
- 参考資料
- 議論ログ
- Q:会場からの質問A:発表者からの回答/コメントC:会場からのコメント
C: 品質と再発防止は日本のISPのいいところと悪いところ。品質管理は年配の方が見ている。本当は現場が分かる人が見て、リーズナブルな改善プロセスを問題が起こる前に行うべきなのに、通常は逆。品質管理はセンスが問われる。日本流品質管理は変わっていくべき。
Q: 品質を高める≠お客様満足度を高める。どのように目的意識を共有するのか?
A: 会社自体が非常に若いので同じような価値観で運用できる
A: 年寄りは運用から離れるべき?
A/C:.....(無言)
A: 品質を上げることが顧客満足につながるわけではない、というのは重要だと思っていて、どう頑張るとお客様が満足するかを探って行きたい。がんばったからといって、報われるわけではない。
C: 壊せるネットワークを作らないと教育にならない。ネットワークを壊さないと絶対覚えられない。壊せるネットワークを作るのが自分のこれからの仕事だと思ってる。新しい人に、壊していただく!
Q: 泥臭い話を聞きたい。夜間のエスカレーションどうしてます?
A: 電話エスカレーション。Opsは、pagerシステムを持っている。Noc が、ある電話番号に掛けると、その週の当番のOpsが出る。
A: NOCに当たるところが24hいるのでそこが電話する。現状はがんばってDC長等が電話に出るしかない。今後はNOCで頑張るようにしたい
A:シフトで回していて、シフトのオペレータがDCにいるようにしている。エスカレーションは、自分だったりリーダーだったりに連絡がいく。今後は、シフトのオペレータも、判断できるように、エスカレーションが減るように、オペレータ自身も考えていく必要がある。
Q: エスカレーションする先自体をグルーピングしている運用をしているところもあると聞いている。ついつい特定の人に電話がかかりがちになってしまうような気がする。(「あの人は夜中に電話かけると機嫌が悪い」とか)
A: エスカレーションは明け方にかかってきがち。とっても機嫌のわるい時間帯(笑)
Q: エスカレーション受信時に手当てって出てます?
A: (会場: ほとんど手を挙げない)
Q: エスカレーションのシフトが決まっているところ
A: (会場: 20%くらい)
Q: 手当てが出てる人
A: (会場: ほとんどいない)
Q: 属人的に、特定の人にかかるところ
A: (会場: ちらほら)
Q: 運用者の評価が減点方式なのが問題。加点的ならモチベーションUpする減点に評価されてる人いる?
A:(会場: しーん...)
Q: うちは加点方式だ!っていう人
A: (会場: 1人だけ)
A: GINは加点方式だと思う。
A: 自分が必要だと思ったらチャレンジすればいいという雰囲気。ただ、最終的には、やったことが皆の役に立っているかどうかで評価が決まっていくと思う。
Q: ツールを使った以上、減点評価はありえない
A: 人を責めずにツールを改善していく
Q: 運用をずっとやっていると体が持たなくなってくるので、自動化してきた。開発から運用に無茶振りを受けたらどうする?
A: 今のところ、無茶振りを受けたことはない。OPS上がりのDEVが多い。10年選手以上のベテランのDEVが多く、阿吽の呼吸が分かっている側面もある。ただ、断らなくてはいけない時は、理由を言って断っている。
Q: アメリカでは、ある程度まで追求して、全体的に見てそれほど大きくない問題であればスパッと見切る、という話があったが、誰がそのあたりを判断をしているのか?
ex: 顧客からの無茶な要求,原因の分からないトラブル
A: opsのボスが判断している。誠意を持って調査をして、それでもダメならやめよう、という判断。
C: 運用部隊は、お客さんに対してサービスの品質を支えている最前線。昔、X.25をやっていた。運用者も約款で規定されているサービスレベルを理解したほうがよいのでは?その上で、お客様の期待値が約款と食い違う場合が多いので、そこはどう対応するかを考えた方がいいのでは。
Q: 年寄りはどうすればいいのか?
A: 年寄りでもがんばるか、もしくは、現場を理解出来るマネージャーになる。後者になったら、ミスを憎んで、人を憎まず。これは大事!
名言「ミスを憎んで人を憎まず」