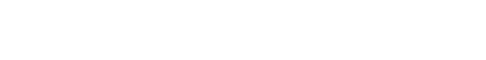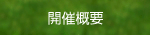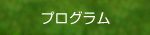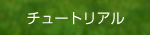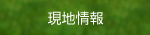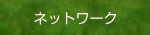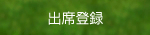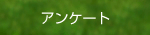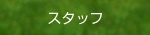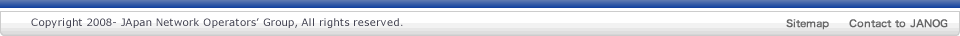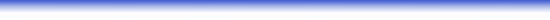
JANOG update & Open mic
- 概要
- 本セッションではJANOGの運営について会場のみなさまとディスカッションする時間を設けます。イメージとしてはIETF のIABオープンマイク、IAOCオープンマイクのような形態を想定しています。はじめに通常のJANOG updateのご報告をして、その後運営委員が全員登壇し、会場のみなさまからご質問やご意見・ご提案をいただきます。ミーティング運営の在り方、ほかコミュニティとの連携、JANOGが価値ある団体でいるためにどういう活動をすべきか、JANOGとして必要な機能、などざっくばらんに話し合う時間にしたいと考えています。
- 発表者
- JANOG運営委員
- 資料
- 資料: JANOG Update
- 議論ログ
- Q:会場からの質問A:発表者からの回答/コメントC:会場からのコメント
<I18Nについて>
Q: 運営委員から通訳側の負担ってどう?A: 楽しい。自分も理解できるからサマライズしてくれるのはありがたい。日本語以外が来た場合はベストエフォートでいいよね。通訳は時間が倍かかる。資料だけバイリンガルにするというのもありだと思う海外の発表者を迎えるのはいいと思う時間が限られているので、外国の方の発表を日本語でやってもらってディスカッションだけ外国の方に加わってもらう今後の国際的なつながりを作る上では外国の方を受け入れるのはいいと思うJANOGの発表は日本語だけでやっているともったいないC: ミーティングで英語大丈夫というのは別の話英語全くダメな人は話に付いていけない日本のコミュニティに撮って重要であれば有益C: 資料が事前公開されていたのは大変ありがたいC: 自動翻訳の技術が普及してきているので使ってみてはいいのでは?C: google transrateに流し込んだら英語の資料ができる、みたいなのがいいなC: プレゼンテーションをする人の思いが一番重要C: だから、オリジナルの資料で制作者がプレゼンテーションするのがいいと思うC: 受け持つセッションがどうしても英語の資料になったり、英語の話者しかいない場合が多いC: 英語発表の手伝いをする人たちと、それをできない人を結びつけることができるといいかもC: I18Nの取り組みがあると思う<インターネットのためにコミュニティができることについて>
A: レイヤの高い話が聞きたいと思う人が多いが、そういうほうに行くのも重要C: JANOGが業界に何ができるのかいつも考えているJANOGのスタッフが毎回入れ替わるのはとてもいいと思う今回はハードルを下げるようにいろいろ考えた。いろんなものを提供できるよう努力した。何かしらお土産を持って帰ってもらいたい。C: 結局、技術はかわっていくと思う。もう1つ上のレイヤだとDEVOPSというのがある。技術は結局混ざっていくいろいろ難しいところはあるC: インターネットのルールを決める時などにパブリックコメントの募集がされることがある。コミュニティはこんな意見だよ、と言ったりするのだが、実際の現場はこうだよ、と伝えられると、理解が深まる。しかし、いきなり意見を、と言われても、運用者の側も、何を言えばいいのかわからないだろうし、どうやって行けばうまく意見を言ってもらえるのか、考えている。C: こういうミーティングができていることが、コミュニティに対する評価だと思うミーティングをやってくれるだけでもありがたいレイヤが上の人たちから見ると、JANOG参加者はレイヤが低い傾向があると思われてる?A: 初参加の方へ「参加のきっかけは?」C: 3年くらい前に聞いたのがきっかけ運用者の生の声を聞いて「自分の運用はぬるくていいのか」などを考えたとても有意義な場だったC: ネットワークを初めたばかり「JANOGというのがあるから行ってこい」と業務は研究開発系。運用の話をどう拾うかが重要だと感じた