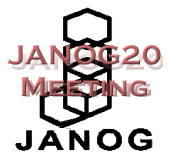
|
|

会場周辺ATM情報
■ 金融機関ATM関連 □ 網走信用金庫 帯広支店 370m □ 帯広信用金庫 駅前支店 400m ・エスタ帯広内ATM(東館1階) 200m ・長崎屋帯広店内ATM(
Obihiro
(July 5, 2007 10:23 PM)

空と川と大地を体感!
国内有数の広大な平野と、大雪山系を水源に太平洋に注ぐ十勝川、年間を通じて晴れわたる日が続く大空。十勝地方では四季折々に豊かな自然を満喫することができます。 特に夏のこの時期は、北海道の大自然を感じるに
Obihiro
(July 3, 2007 5:22 PM)

鉄道でゆく JANOG20
今回、帯広で開催されるJANOG20ですが、参加者の大半の方はJALの直行便で十勝帯広空港。ちょっとこだわりのある人でもANAで新千歳空港からJR特急で帯広、というのが一般的な経路でしょう。 東京から
Obihiro
(June 28, 2007 11:25 AM)

IPv4アドレス枯渇を世界各地で、そして帯広で考える
IPv4アドレス枯渇を世界各地で、そして帯広で考える IPv4アドレス枯渇が叫ばれた1992年頃にはCIDRやNATが導入され、 延命されてきたことは皆さんご存知のことと思います。 また、並行してI
Column
(June 25, 2007 4:10 PM)

IP Anycastで見えてくるインターネットの接続図
IP Anycastで見えてくるインターネットの接続図 IP Anycast を使った運用自体は馴染みのない方が多いかもしれませんが A.DNS.JP では Anycastを使って運用している事をご
Column
(June 25, 2007 4:09 PM)


Google Search
■ インターネットオペレーションを語る

日時
スピーカ
担当プロデューサ
担当PC

この10年の間、インターネットは大きな発展と変化を遂げてきた。
一つの産業における10年の歴史は、それほど長いものではないと考える事もできるが、
ことインターネットについては10年の間に利用する技術、とりまく環境が大きく変化している事は紛れもない事実である。
JANOG は1997年に設立されたネットワーク運用者のコミュニティとしての組織であり、今年で満10年を迎える。
そこで本プログラムでは
- JANOGがインターネット運用の歴史においてどう関わってきたか
- JANOGが現在のインターネット運用とどう関わっているか
- JANOG設立当時のインターネット運用とは
- インターネット運用の現状とその問題点とは
- 「インターネット運用/コミュニティ」の今後とは
これらを色々な立場を持つ発表者に語ってもらい、我々が経験した大きな変化や今後のオペレーションとそれを取り巻く環境について考え、議論したい。
Program Producer
橘 俊男
橘 俊男
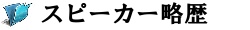

|
1986年 東京大学理学部情報科学修士課程終了後、国内大手通信会社に入社。 国内最大級ISP のネットワーク設計、構築、運用を担当。 その後、JPNIC-IP WG主査や、ICANN ASO 副議長を務める。 2002年 インテック・ネットコア設立時に専務就任、現在、代表取締役社長。 最近ではIPv6の実現・普及啓蒙活動に従事しており現在、 • (社)日本ネットワークインフォメーション センターJPNIC 理事(IPv6 分野担当) • IPv6 Forumのボードメンバ • (財)インターネット協会IPv6デプロイメント委員会議長 などを務める。 |
|
2000年 グローバルクロッシング入社 MPLS/IPネットワークのアジアネットワークを設計、構築 2003年 アジアネットコムに社名変更 MPLS/IPネットワークのグローバルネットワークを設計、再構築 • アジアネットコムジャパン株式会社 バイスチェア • APOPS (Asia-Pacific Operations Forum) Co-Chair • MPLS Japan Program委員 |

|
1993年03月 北海道大学農学部卒 1993年04月 株式会社SRA入社 1995年01月 ネットワーク情報サービス株式会社入社 1996年10月 株式会社デジタル・マジック・ラボ入社 1999年10月 IP Infusion設立 現職: IP Infusion Inc CTO |

|
1987年 九州大学 工学部電子工学科 修士課程終了 同年4月 (株)東芝 入社 総合研究所にて ATMネットワーク制御技術の研究に従事。 1990年より2年間 米国ニュージャージ州 ベルコア社 1994年より2年間 米国ニューヨーク市 コロンビア大学 CTR(Centre for Telecommunications Research)にて客員研究員。高速インターネットアーキテクチャの研究に従事。 1994年 ラベルスイッチ技術のもととなるセルスイッチルータ技術を IETFに提案し、その後、セルスイッチルータ の研究・開発・マーケティングに従事。IETFのMPLS分科会、IPv6分科会では、積極的に標準化活動に貢献している。 1998年10月より東京大学 大型計算機センター助教授、2001年4月より東京大学 情報理工学系 研究科 助教授。 2005年4月より 現職(東京大学 情報理工学系研究科 教授) • WIDEプロジェクトボードメンバー • MPLS-JAPAN代表 • IPv6普及・高度化推進協議会専務理事 • JPNIC副理事長 • ISOC(Internet Society)理事(Board of Trustee) 工学博士(東京大学) |