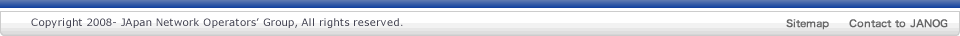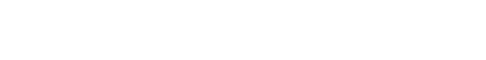


【プログラム紹介】 インターネットの決め事の決め方
これまで何度かJANOGミーティングのプログラムでも取り上げられながら、わかりづらく敬遠されがちなインターネットガバナンス。本プログラムでは、身近な問題とともに議論し理解を深めていくことで、インターネットガバナンスへの関心を高めてもらおうと考えています。
本プログラムの内容について、登壇者の土屋 太二さん(ビッグローブ株式会社)と担当プログラム委員にお話をうかがいました。 (聞き手=JANOG36企画編成委員)
普段の業務内容とインターネットガバナンスとの関わりについて教えてください
土屋: ただの“いちネットワーク運用者”で、インターネットガバナンスのスペシャリストではありません。
これまで、インターネットガバナンスの話題に触れてきてどのように感じていましたか?
土屋: これまで何度か、JANOGミーティングでインターネットガバナンス系プログラムに参加しました。なんとなく雰囲気はわかるものの、「専門用語が難しい」「登場する団体が多すぎて、それぞれの団体の役割や立ち位置がよく分からない」「“誰”が“どこ”で“どのように”闘っているのかイマイチ想像できない」などの理由で、別世界の人の話だな、と心の中で感じていました。
今回、登壇するのはどういった理由でしょう?
土屋: インターネットガバナンスについて、私のように感じているJANOGerの方は決して少なくないと思っています。インターネットガバナンスを”自分ごと”として考えるには、こういったモヤモヤを無くした上で、最前線でなにが起きているのかを正確に捉えることが第一歩目として必要だと感じています。
インターネットガバナンスについて解らないことを明確にするために、インターネットガバナンスのスペシャリストである前村さんを質問攻めにし、そこで解ったことから、現在のインターネットガバナンス最前線で議論されているテーマを自分の言葉で噛み砕いて伝えていきたいと思ったからです。
参加者の皆さんに伝えたいことをお願いします
土屋: ネットワーク運用者とインターネットガバナンスがどのような距離感で付き合っていくべきかみなさんと一緒に考えていきたいので、議論への参加をお願いします。
担当プログラム委員から、プログラムについて一言お願いします
「インターネットのガバナンス」と言うと少し身構えてしまう自分が居ました。しかし、今回プログラム発表者の思いを受け止めて改めて考えてみました。
『わたしたちの○○○を、もっとよくしていくために。』
技術的なスケーラビリティやアベイラビリティ、スループットを「もっとよくする」活動と、番号資源をどうしようという「もっとよくする」活動はそのフィールドがちょっと異なるだけでモチベーションの根源は大きく変わらないような気が今はしています。ガバナンスというと覇権争いや、現行秩序への挑戦など何やらおどろおどろしいことを想像してしまいがちですが、「自分たちが活かされているフィールドをもっとよくしていく活動の一つ」ととらえるとハードルがぐっと下がるんじゃないかと思います。
気軽にとは言いませんが、自分たちの技術的な活動との距離感をもっと近くに感じるプログラムですので、皆さんと「もっとよくしていく」輪を大きくできたらプログラム委員として嬉しいです。
リンク
今気になるインターネット・ガバナンス (JANOG32)
未来の二つの顔 ~電話とインターネットの狭間で~ (JANOG33)
インターネットガバナンスがよくわからない? 本音でひざをつき合わせて語るBoF~ “I CAN” not understand ICANN? ~ (JANOG34)
まだまだ続くインターネットガバナンス。ガバナンスってナンスか? (JANOG35)
もっと距離を縮めたい ♥ オペレータとポリシー (JANOG35.5)
インターネットの決め事の決め方 (JANOG36)