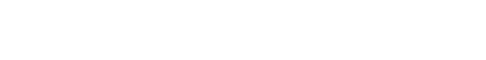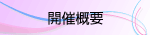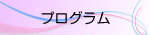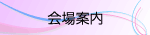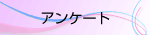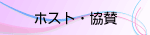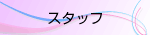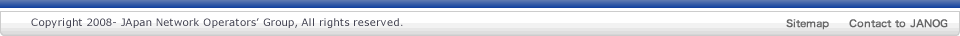JANOG28
プログラム詳細
- タイトル
- インターネット・アーキの限界について議論しよう
- 概要
-
例えば、v4アドレス枯渇からv6の普及が本格化しようとしているが、v6はアドレス空間については解決したものの、その他の問題をあまり解決していない。
あるいは、ルータにおけるFIBエントリ数問題に関しては、階層化FIBの導入により延命がはかられたと考えられる。
トラフィック量の爆発、エンドツーエンドのアーキテクチャ(NAT・プロキシー・キャッシュ)、PIアドレス、マルチホーム、QoS(保証・優先制御)など、現状のInternetアーキに内在する数々の問題点や限界点について、現在の状況を整理し、今後何が必要になってくるのかについて議論したい。 - 発表者
-

菊地 俊介 (情報通信研究機構(NICT))
1999年富士通研究所に入社。
途中、IP電話業務のSEとして現場運用を経験しつつ、主に研究所でネットワーク技術の研究活動に従事する。
近年はクラウドコンピューティング研究センターに所属し、データセンターネットワークの構築・運用管理技術やデータセンターへのアクセスネットワークに関する技術開発に従事。
2011年4月より情報通信研究機構(NICT)に出向し、新世代ネットワークに関する技術開発とその推進活動を担当している。
なお、JANOGへの参加は近年になってから。

水越 一郎 (東日本電信電話株式会社)
パソコン通信黎明期の商用サービス (ASCIINET) でシステム運用・開発を担当。
その後、ISP数社 (ネットワーク情報サービス、東京インターネット) を経て1997年NTTに入社、OCNの運用に携わる。
2006年10月から東日本電信電話株式会社、主にFLET'S関連サービスの運用・開発に従事。
- 事後資料