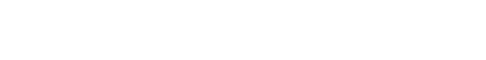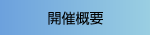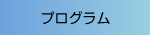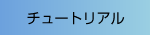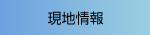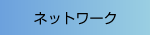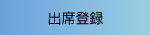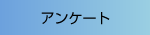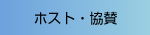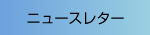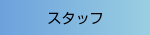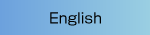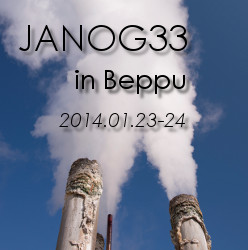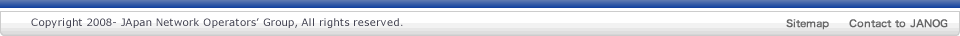JANOG33スタッフの吉野と申します。
前回に引き続きプログラム紹介の第3弾は、「グローバルインターネットにおける大容量トラフィックとリソースマネージメント」をご紹介したいと思います。グローバルインターネットにおいてトラフィックを運ぶ悩みはたくさんあるようですが、今回の発表では次の悩みに対する現時点での一つの解を共有いただけるようです。
- トラフィックのオリジンが頻繁に大容量で移動する
- ケーブルごとの通信コストや品質が違う
- 可能な限り遅延を抑えたい
JANOG33 注目プログラムのご紹介 [第三弾]「グローバルインターネットにおける大容量トラフィックとリソースマネージメント」
- プログラムページ
- グローバルインターネットにおける大容量トラフィックとリソースマネージメント
- 発表者
- 清水 香里 (エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社)
- 聞き手
- 吉野 純平 (JANOG33実行委員)
インタビュー
- プログラムの見所はずばりどこでしょうか?
- MPLS-TEをどのように活用して悩みを解決しているのかをぜひみていただきたいです。
- どんな人に聞いてもらいたいでしょうか?
- トラフィックコントロールされている方、したい方に、工夫や自動化のポイントを共有します。グローバルでトラフィックを運ぶ場面でのエンジニアリングの話ですが、考え方は他の場面でも役立つと思っています。
- どんなことを考慮してトラフィックコントロールされているのでしょうか?
- IPだけのネットワークでは、通信コストや遅延を最適化しづらくMPLS-TEを使っています。ルータ間で使う帯域を決めLSPを作成することで、IPのプロトコルでの最適パスとは異なるパスでトラフィックを運んでいます。コンテンツはCDNの活用等で絶えず移動を繰り返し、大陸を超えての移動すらも発生しています。このためLSPで確保する帯域の再調整を頻繁に行う必要があり、これを自動化しています。
- 事前にどのような知識があるとより楽しむことができるでしょうか?
- 基礎的なBGPの知識やMPLSにおけるLSPが何なのかがわかっていると理解が深まるかと思います。発表の中でパスアトリビュートの紹介をしますが、LSPの作り方、使い方をまず理解していただくのがよさそうです。
以上がインタビューさせていただいた内容です。私にはMPLSの基礎知識がなく、理解ができるか不安がありました。しかし、モチベーションや基礎的なことを説明いただくと、とても理解が深まりました。どんなトラフィックコントロールをどんな目的で行い、それをMPLSで実装する場合の方法の1つをわかりやすく聞くことができるプログラムになると思います。その神髄をより感じていただくためも基礎的な内容を事前にしっていたほうが、より楽しめるかと思います。以下に過去に公開されている資料のリンクをスタッフで集めました。ぜひとも1/9にオンラインで実施されるMPLSチュートリアルに参加いただき、本プログラムを味わっていただければと思います。
- JANOG33のチュートリアル
- BGPの基礎
- MPLS関連
以上、第三回のプログラム紹介でした。
JANOG33参加登録をよろしくお願いいたします。