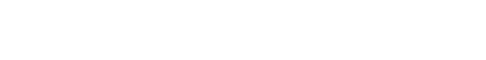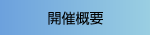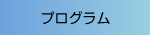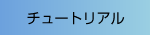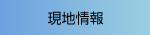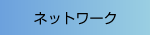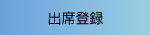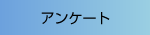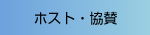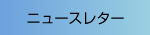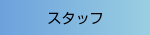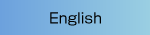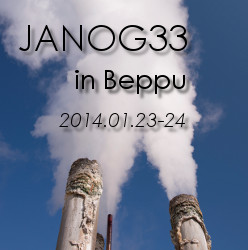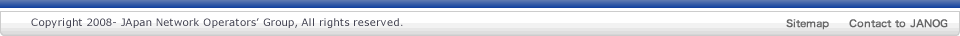JANOG33 注目プログラムのご紹介 [第一弾]「SPDYによるトラフィックの変化」
SPDYはHTTP通信の高速化を図るクライアント・サーバー間の技術として近年注目されてきていますが、Google ChromeがオプトインによりGoogleのSPDY Proxyへ接続する機能が搭載されたことで、もはやクライアント・サーバー間だけの問題ではなく、インターネットのトラフィックなどに影響を与える恐れがあり、ネットワークエンジニアとしても動向に注視していく必要がありそうです。
- プログラムページ
- SPDYによるトラフィックの変化
- 発表者
- 吉野 純平 (株式会社ミクシィ)
- 聞き手
- 松本 拓也 (JANOG33実行委員)
インタビュー
- なぜ、応募しようと思ったのか。背景の深堀
- 過去に今回の内容について、janog@janogにメールを投げたことがありました。SPDYによるforward proxyが流行るといくつかの視点において考えなければならないことが増えるだろうと考えております。これについて議論したいと思います。
- プログラムの見どころはズバリ
- いろいろなインターネット回線やアプリケーションへの複数レイヤでの問題提起をしたいと思っています。
- どんな人に聞いてもらいたい?ターゲットは?
- データセンターで、webホスティングをされている方
- ISPさんで、増強計画等を作られている方
- コンテンツ事業者で、アプリ開発されている方、proxy等の担当の方
- 議論したい内容、目指すべき到達点
- 目指したい所は、「SSL対応の目的と範囲を決めて進めましょう、コストを抑えるためのドメイン名の決め方をしましょう」といったところでしょうか。この目的なので、SPDYを導入しましょうというところは、その先の話です。この先で、http2.0なども話題になっているので、SPDY SPDY言う気はありません
- SPDY proxy の利用は今後進むのでしょうか?また、それによってどのような影響がありそうでしょうか?
- 既にモバイルで0.数%のトラフィックがProxy経由で流れています。良い面で見れば、モバイルのセッション数が減ることで、ユーザーの体感レスポンスが良くなる例も公開されています。影響としては、通常あまりCSPはGoogleとピアすることはありませんが、Proxyの利用が進むと、Googleとの「ピア」の影響が大きくなるかもしれません。
- SPDY Proxyの懸念点としてはどんなことが考えられるでしょうか?
IPアドレスがより識別情報として成り立たなくなると思われます。また、リクエストヘッダーにIPの情報が入ってくると思いますが、そもそも、そのアドレスを信用して良いのか、という問題もあります。
そもそもHTTPの認証情報などもGoogleで見ようと思えば見える状況。未だにHTTPで認証しているところもありますので…
また、これがデファクトスタンダードになった場合に、Googleに依存する状態になることが懸念されます。例えば、ある日突然、ブラウザでProxyサービスをサポートしなくなった場合や、GoogleがPayed Peerとなった場合、Googleでシステム障害が発生した場合など。
- 現状の解決策は?
- 直接通信にするには、SSL化するかしかないのではないでしょうか。全てをSSL化するのは難しいと思いますが、皆さんで考えてみませんか?
以上、吉野さんには発表前にも関わらず、核心に迫るとても興味深いお話をお聞きすることができました。お話をお聞きして、SPDY Proxyによって、無縁だと考えていたようなCSPやISPなど様々なステークスホルダに影響が波及する可能性もあり、今回のJANOG33でも是非とも会場の様々な方のご意見をお聞きできることを楽しみにしております。