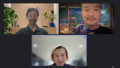Day1 (2024年7月3日(水)) 17:00~18:00にIIJホール(天平ホール)にて開催される、「NWエンジニア的RPAの使い方 -作業・テストの自動化を考える-」の発表者の秋山剛志さんと山岡裕美さん(ともに京都工芸繊維大学)に、本プログラムについてお話を伺いました。

応募したきっかけ
DX化を進めるためにRPAツールを試験導入しましたが、RPAツールは、どちらかというと事務部門の仕事効率化のために利用されることが多いイメージがあります。
しかし、技術部門でもうまく使えば作業の自動化・効率化ができるのではと思い試行をはじめました。働き方改革やらいろいろあって、人手が不足しています。せっかく作った自動化の仕組みも、作った人やプログラムに詳しい人がいないと修正・追加が行えないと使えなくなるという問題がありました。
自動化のシナリオを作るのに専門的な知識がなくてもできるRPAツールを使うことによって、誰でも自動化へチャレンジができるのではないかと思い、今回、本学での事例を紹介することにしました。
アピールポイント、議論したいこと
本学では、DX化を進めるためにRPAツールの試験導入を行いました。事務作業の効率化が目的でしたが、RPAツールを使うとマウスやキーボードの動きを記録し、再生することができます。ネットワークやサーバを停止した後に、動作確認を行っていますが、同じような項目を、接続するネットワークを変更して何回も実施する必要がありました。RPAツールを利用することによって、この動作確認を自動化できないか試行した事例を紹介します。
これまでJANOGでも自動化について多くの事例発表や議論が行われてきましたが、自作のツールやRobotFrameworkを使ったものが多かったという認識です。これらのツールやアプリは、作った人やプログラミングに詳しい人がいないと、自動化する機能の変更や追加等が難しいです。
一方、今回使用したRPAツールは、Windowsにしか対応していませんが、簡単な操作で作業を自動化することができます。どのような操作を自動化しているかわかりやすいため、自動化の技術継承がやりやすいです。
議論のポイントとしては、自動化するときに、できる人にお任せしているとその人が異動や退職した後に困ることが多いと思いますが、その辺をどうやって解消していますか?
また、操作が自動化できるRPAツールのもっと面白い使い方があれば教えてください。
JANOG54参加者への期待
自動化でのお困りごとや工夫していることを聞いてみたいです。
最後に
自動化ってとても便利なんですが、仕組みを作るのが大変だし、誰でも使える(シナリオを作れる)ようにするのはもっと大変です。今回は自動化を簡単に実施する方法を紹介しますが、そうやって作ったものをどうすれば継承していくことができるのかみんなで考えたいと思います。